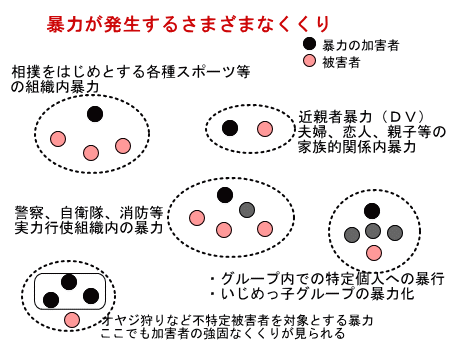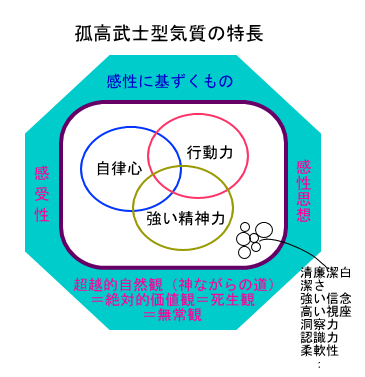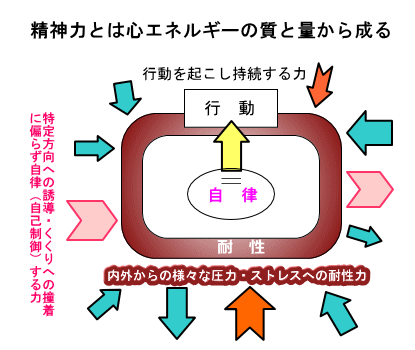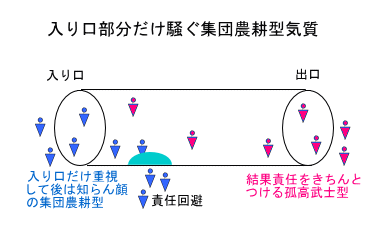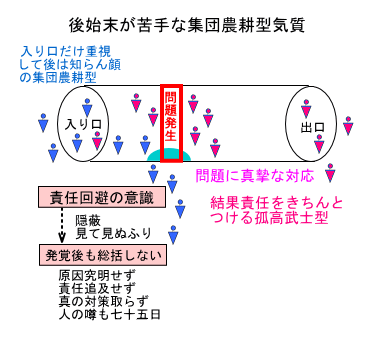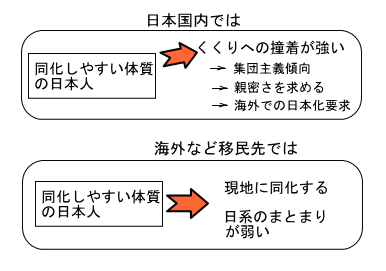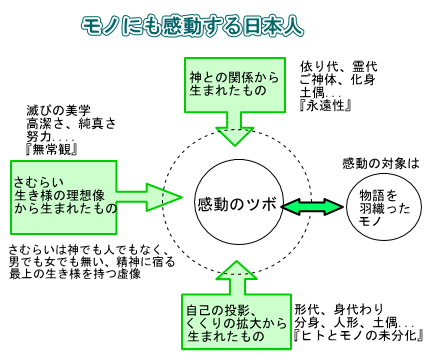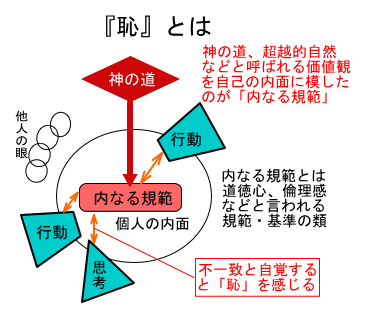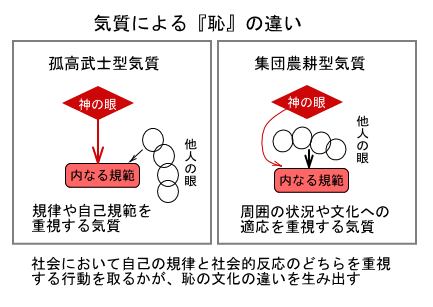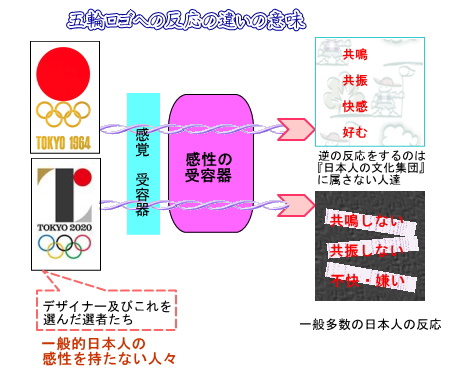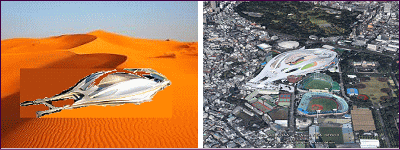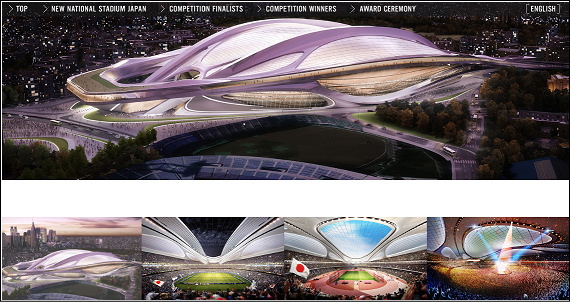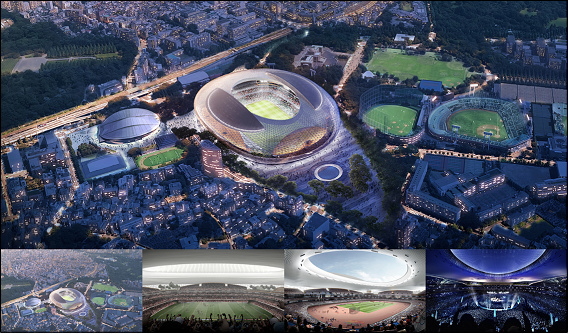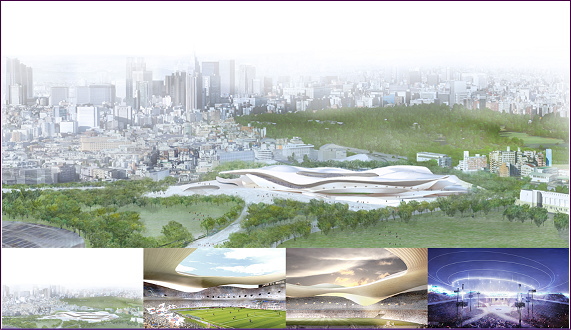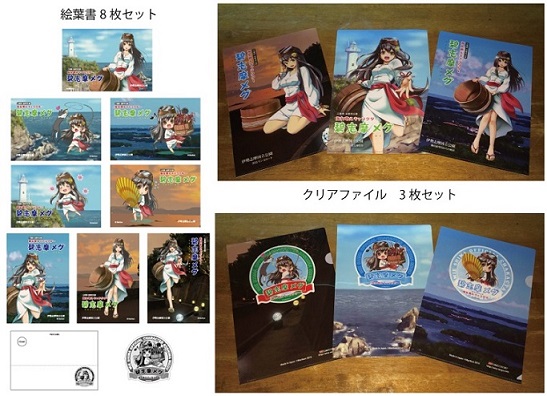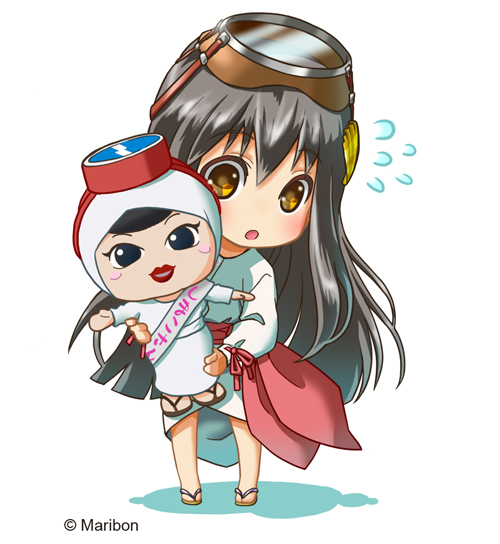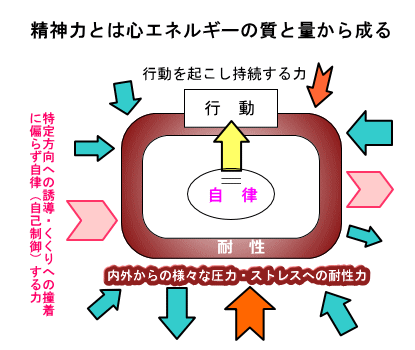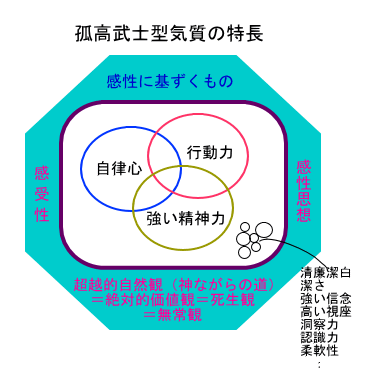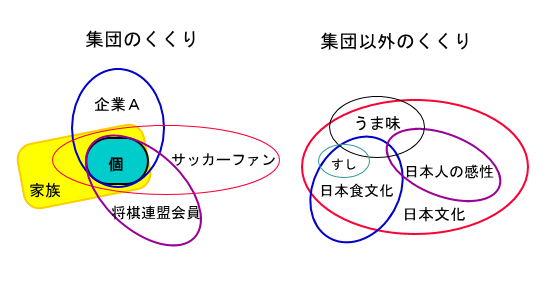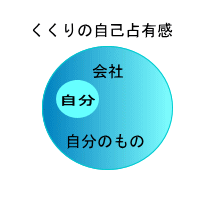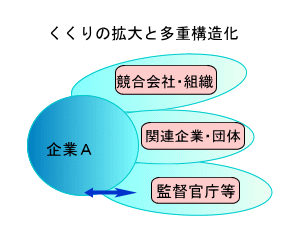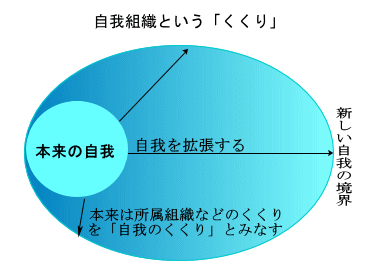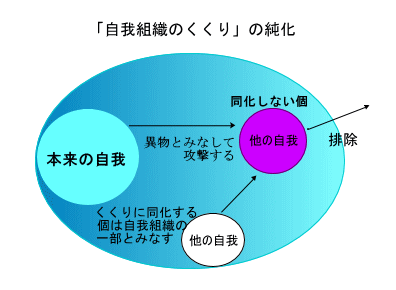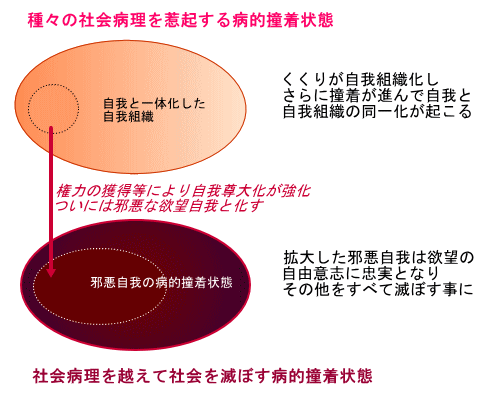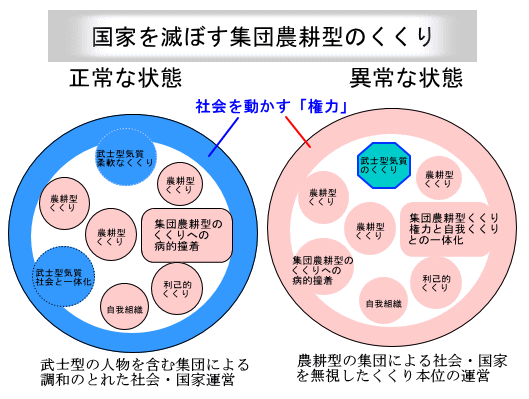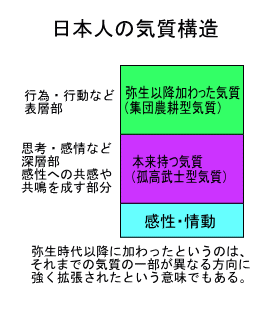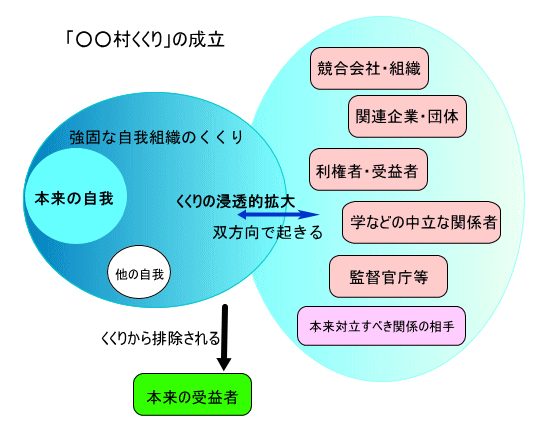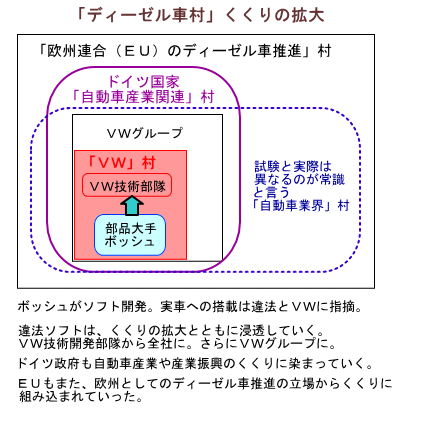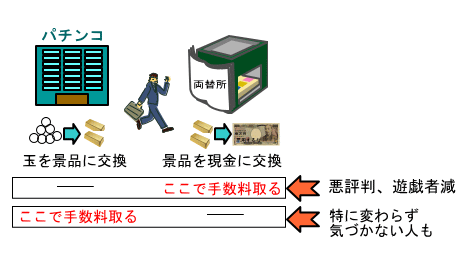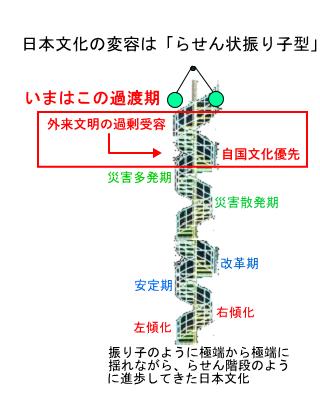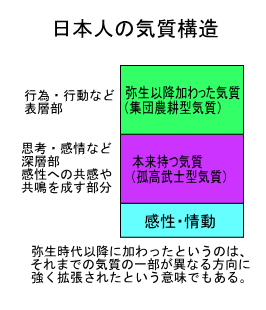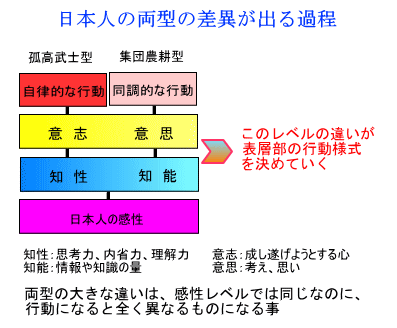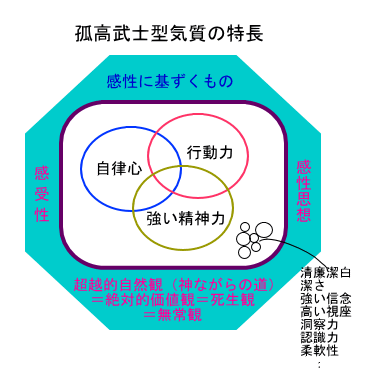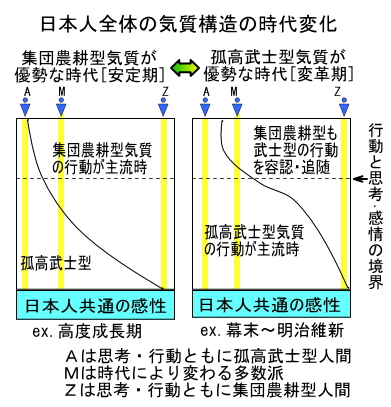(追)このコラムは今から10年も前のものであるが、平成から令和に、安倍総理から菅総理に、そしてコロナ前からコロナ後に、今まさに同じ状況にあるといえるのではないだろうか。未だ色あせぬ内容であることは、むしろ悲しいのだが。 2020.09
話題を決めて話をしたり俳句を作ったり、人気タレントと小学生が、いろいろなことをやるテレビの人気番組がある。このまえ、「大人のここが理解できない」というテーマについて子供たちの意見を聞いたところ、小学生の女の子が、40過ぎの女性が若い人のようなミニスカートの派手な格好をしていたが似合わない、「どうしてあんな服を着るのだろうか、もっと会ったものを着れば良いのに」と発言していた。服装が似合う、似合わないは必ずしも年齢とは関係しないので、一概にはそう決め付けられないのだが、そういわれてみればたしかに最近その手の人を見かけるようになった気がする。そしてこれが必ずしも若づくりと言うことだけではなさそうに思われる。
一部のデパートなどでは、中年以上の女性を対象とした新しい試みとして、色柄やデザインは若い女性向けとおなじで、サイズだけ中年向けの服を取り揃えたコーナーを開設したところ、評判も上々だそうである。この狙いは、最近の中年やシニア世代に、『もう一度人生をやり直したい』と言う願望が多く見られるようになった、それに基づく戦略だとインタビューでデパート側が答えていた。この手の市場は今後個人消費の中でも拡大をして、個人消費全体の1/6を占めるまでになるそうである。そうしてみると、先ほどのちょっと似合っていない服装の人が増えたのもうなずけることなのかも知れない。
この『人生をもう一度やり直したい』と言う願望は女性だけではなく、いわゆるサラリーマン層に、広く深く広がっているような気がする。現在不況の真っ只中、それも雇用と言う点では、深刻な状況に入っている今の世相からして、好まずともリストラなどによって新しい人生を歩まざるを得なくなった人も多いと思う。こういう人たちまでひっくるめて、人生のやり直し願望組と決め付けるわけにはいかないかもしれないが、もう一度別の人生に挑戦してみようと言う気持ちで、早期退職制度を活用した人も多いのではないだろうか。私はこれを「人生やり直し症候群」とひそかに呼んでいる。
「人生やり直し症候群」の年代は何歳ぐらいなのであろうか?昭和20年の敗戦後に生まれた団塊の世代と呼ばれる人達から始まり、10年一区切りと考えれば、20年代に生まれた、45歳から55歳位の間の人々を指すことになる。この世代もさらにいくつかに別れるような気がするが、他の世代とは異なる精神構造の基盤を有するように思う。戦後民主主義の恩恵を受けて、と言えば聞こえは良いが、これまでの価値観を根底から破壊され自己を喪失せざるを得なかった親に育てられた最初の世代である。したがって、価値の大転換を目の当たりにして、一種の軽い虚無観、ニヒリズムを受け入れやすい、それでいて、そのような主義思想そのものを信じることができない世代である。いわゆる進歩的教育者と言う名の教師達にゆがんだ教育を押し付けられながら、戦前までの日本人としてのアイデンティティを持った親の躾がわずかではあったがまだ残っていた世代と、反動で自由と言う名の放任主義で育てられた世代とに別れるのだが。それでもなお、この世代にはいくばくかの救いがあるのは、貧しさをおぼろげながらも知っていることであろうか。いわゆるコッペパンの味を知っているのもこの世代だけであろう。戦後の日本人が、高度成長の経済的な恩恵をこうむるようになるにはもう少し時間がかかったのである。このことが、それ以後の世代との大きな違いを生むことになったのではないだろうか。
なぜ症候群なのかと言えば、その原因が多岐に渡るにもかかわらず、症状としての目に見える行為(現象)はみな同じだからである。
ひとつは過去を水に流して清算し、もう一度ゼロから始めたい、ふたつ目は、服装などに現れているように、年齢とか既成の概念にとらわれず、自分が良いと思うものを選択し、良いと思うことを自由に行いたいというもの。
そして、これは、そうあって欲しいとの願望も含まれているのでははあるが、単純な成長主義、金権主義から距離を置くことになる。かつてこの世代は、ヒッピーと呼ばれる反体制の人々を生み出している。しかし、日本でこれがあまり受け入れられなかったのは、単純な反対のための反対を好まなかったのと、より良い暮らし、言い換えれば成長や進歩そのものを悪とはしない考え方によったのだろう。症候群はこのような精神性の土壌から生まれているのではないだろうか?海外での老後なども、日本より生活がすごしやすく、環境も良いことを前提としての話であり、決して田舎の隠遁生活と軸を同じくするものではない。
では、人生のやり直し、すなわちもう一度というのは、バブルの夢よもう一度、ということなのであろうか?そういう人たちも一部にはいるであろう。だが、そういう人たちはなかなか人生やり直し症候群にはかからないようである。むしろ、バブルガンの末期症状であろう。大多数の人の思いはそうではあるまい。
これまで家庭も顧みずモーレツ社員として、会社や社会の一歯車として自分を犠牲にしながら、すくなくともそう感じるよう自分に言い聞かせながら、全速でここまで時代をかけ抜けてきた。そして、それが多少なりとも豊かな老後の夢を描いてくれるのならばまだしも、そんな自分の生き様とその価値観を否定され、あとにはずたずたに引き裂かれた自己だけが残された。これまでのがんばりが無駄な徒労だったとしたのならば、いったい自分の人生は、自分自身は何だったのだろうかと思い悩んでも不思議は無い。そのやりきれない思いが、もう一度やり直したいとの気持ちをさらに強くする。
すべての過去を水にながして、やり直したいというのが大方の偽らざる気持ちではないだろうか。成功もあったかもしれない、人並みの生活や幸せも有ったかもしれない、だが、それすらいまとなっては遠い夢、見果てぬ夢だったとしたら。そんな人々に残された夢は、もう一度全てをやり直すことなのかもしれない。
精神的にも、さらにひどければ、経済的にも満たされない状況にある自分を振り返るとき、人生のページをめくって、白いキャンパスからもう一度始めたいと思うのである。
日本人が「すべてを水に流す」と言うと、反省していないとか、過去の教訓が生かされていないなどと批判されることがある。それは一面の真理ではあろうが、我々日本人にとっては別の意味がある。欧米人にとってはもう一度やり直すと言うことは、悪かった点、改善の余地のある点を正して、元の正しい道にもどす、という意味合いが強いのではないだろうか?それにたいして、日本人は、良かったことも、悪かったことも同じように忘れて、まったく白紙の状態から始めたいとする心の動きがある。新年にはまったく新しい再生された魂になることを願う根源的な民族の精神構造があるように思う。
疲弊し、行き場を失い、汚れた魂を抱えてもがき苦しむ今の日本人が、もう一度再生し生まれ変わっていく。『人生やり直し症候群』が、そんな姿の第一歩であることを願わずにはいられない。無論、自分自身のこともそのなかに含めて。
平成13年12月